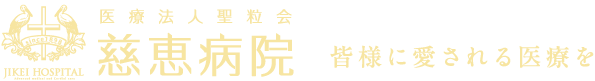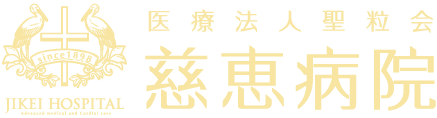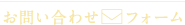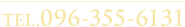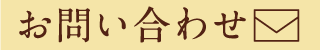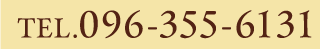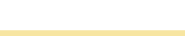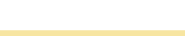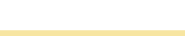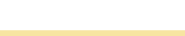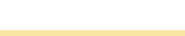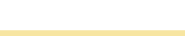第1回、第2回放送内容は児童養護施設の子どもをはじめとして多くの関係者を傷つける内容でした。しかし、その後の放送分については次第に差別的な表現がなくなりました。あだ名の設定は最後まで変わりませんでしたが、それ以外については大きく問題になる内容ではないと受け止めています。
また、感動的な部分、考えさせられる部分もあり、制作に携われた方々が子どもへの影響に配慮なさりつつ、メッセージ性のある作品を目指されたことがうかがえました。関係の皆さまのご努力に感謝と敬意を表します。
一方で、「最初は過激で抗議を受けたが、その後はいいドラマになって感動した」という評価に落ち着いているようにも見えます。社会はそのように見ても、傷ついてしまった施設の子どもや関係者からは、「こんなことなら、そっとしておいて欲しかった」という声が漏れてきます。
「テレビ局は視聴率のために私たちを利用しているだけで、私たちを理解してくれない」
「児童養護施設をドラマにすれば、関係者から抗議を受けてスポンサーも降りてしまう。リスクのある領域なので近寄らない方が無難」
両者の間にこのような認識が残ったように思います。
今回の問題は社会的養護について、当事者と一般社会との認識の乖離(かいり)を浮き彫りにもしました。
「施設の子を守りすぎると『過保護な子』になってしまい、問題です。そのような育て方をすると強い人間になれません」
このようなお声もいただきましたが、施設現場には「社会の無理解」と映ります。
被虐待児が6割を占め、病的精神状態にも対処しなければならないのが実情ですから。
何が問題だったかの「整理」と「確認」を行わなければ、溝を埋めることはできません。
また、例え日本テレビや制作関係の方々が問題を理解されても、その他の方たちの理解を得られなければ、別のドラマで同じ問題が再発する可能性があります。BPO(放送倫理・番組向上機構)の青少年委員会は、審議入りしない決定を行いました。理由は未公開ですが、放送業界がこの問題に正面から向き合うことを願っています。この問題への対処は、誰が悪いとか誰が罰を受けるという事を決めるものではありません。
“社会的養護”という重く難しいテーマをどのように社会に伝え、理解していくべきかの最低限のガイドライン作りにあると思います。
ドラマに限らず、メディアで社会的養護を取り上げていただく事は重要です。社会がその実情を理解し、問題を認識することで、社会も国も改善へ動き出します。
しかし、取り上げていただく際に準備や配慮が必要であることをお考えいただきたく、私たちの見解を述べたいと思います。
日本テレビの関係者さまが「最後まで見れば、私たちの意図を理解していただける」と述べられ、9回の放送を拝見しました。それを経ての見解を申し上げます。
(1)「ポスト」「ドンキ」「ボンビ」「ロッカー」などのあだ名設定
これらは、児童養護施設の子に対して絶対使ってはいけないあだ名のはずです。施設入所理由をあだ名として用いること自体が虐待にあたります。
その子の心理状態によっては、これらのあだ名で呼ぶだけでもフラッシュバックを来す可能性があり、回復に向かっていた心が再び闇の中へ入り込んでしまうのです。
虐待を受けた子によっては、それほど深刻なものになる可能性があるのです。
しかし、ドラマの中では特に抵抗もなく、あだ名のやり取りがなされました。
今回のドラマを通して、あだ名を以下のように受け止める子どもがいないでしょうか。
・施設の子たちに付けられるあだ名
・そのあだ名で呼ばれても本人は嫌がらずに受け入れている
・周囲の大人も、とがめたりしない
・つまり、施設の子に付くあだ名としては、ひどいものではない
その結果、施設の子が学校で友達から悪意なく「ポスト」「ロッカー」「ドンキ」「ボンビ」と呼ばれることがあれば、このドラマは罪深いと思いますし、実際に「ポスト」と学校で呼ばれ、つらい思いをした子どもの報告がなされました。
例えば、ドラマで太った小学生のあだ名が「ブタ」と設定され、9回放送されたら問題となったはずです。
「ブタ」というあだ名で呼ばれたとき、痩せている人はピンとこないかもしれませんが、太っている人は傷つきます。「ポスト」「ロッカー」「ボンビ」「ドンキ」いずれのあだ名についても、一般家庭の子どもにはピンときません。しかし施設の子の中には、身に覚えのある子や「ひょっとしたら自分は…」と考える子がいます。
全国の施設に3万人の子どもがいて、その6割が被虐待児なのですから。
「ドンキ」は母親が鈍器(灰皿)で交際相手を殴ったことから付いたあだ名でした。大阪府警の発表によれば、平成25年の児童虐待において子どもの目の前で起こった家庭内暴力などの「心理的虐待」被害者が1,500人に至ったとのことです。自分の親や兄弟が暴力を受ける現場に立ち会わされてしまった子どもの心の傷は深いはずです。愛する人が暴力を受ける場面を目の当たりにした子どもにとって、「ドンキ」は冗談では済まされないあだ名なのです。
ドラマの放送が重なるにつれて、あだ名について議論がなくなってきました。
また、当院にいただいたご意見の中にも、「あだ名がひどいとは思わない」と
いうものがありました。その理由を次のように考えます。
①視聴者の多くが児童養護施設に対して実体験がないため想像力が
行き届かず、「施設の子に使ってはいけないあだ名」との認識に乏しい。
②ほのぼのムードの中で出演者が当たり前のようにやり取りするあだ名なので、次第に違和感が薄れる。
しかし、施設の子どもなど当事者にとって、これらのあだ名はひどいものです。
大人はこれらのあだ名を施設の子に投げかけてはいけない、ということを教えなければいけません。
9回のドラマ放送は終了しましたが、果たしてこれらのあだ名がなければドラマは成立しなかったのでしょうか。
例えば、「ドンキ」の母親が交際相手の男性を鈍器で殴ったとしても、「母親が傷害事件を起こした」過去を持つ女の子という設定のまま、「マキ」の名前で良かったのではないかと思います。
「ポスト」もそうです。「こうのとりのゆりかご」に預けられた過去を持つ女の子の設定のまま、「キララ」の名前で通しても9回の流れには大きく影響しなかったと思います。もちろん、「実親が付けた名前を捨てる」という設定を大事にしたい関係者のお気持ちも分かります。しかし、「ポスト」のあだ名を使わなくても、事情の説明や描写は可能だったはずです。「ポスト」のあだ名がなければ行き詰まってしまう展開のドラマではなかったと思います。
「ポスト」をあだ名として使うにあたっては、預けられた子どもたちへの配慮が求められます。この子たちは親が保護や育児を放棄してしまった境遇にあります。
実親に代わって社会が守らなければならないはずです。
本人に責任はありません。
また、望まないのに他者から不当に傷つけられたり貶められたりする原因を背負わされながら生まれてきた子でもあります。 「ポスト」をあえてあだ名として使うからには、その必然性を提示していただくべきでした。
9回の放送が終わっても、未だにあだ名の必然性には疑問が残ります。 失礼な申し上げ方かもしれませんが、「話題性を狙った」「インパクトのある名前が欲しい」という動機の方が理解しやすいのです。 「預けられた子たちへ思いを馳せて設定した」あだ名ではないと思います。
(2)施設長が子どもたちをペットショップの犬と同等と見なし、泣く練習をさせる場面
施設長の言動は数十年前の施設ではあったとしても、現在の施設ではあり得ないものでした。ドラマの中では大人も子どもも携帯電話でやり取りする姿が度々出てきました。その時代設定において、あのような施設長の描写には無理があります。
このシーンについて、「児童養護施設内の虐待を描写することで問題提起をしている」というお声もいただきました。
そういう意図であれば、最近の施設内虐待事例を取材し、それに基づいて虐待シーンを描いていただくべきでした。その上で、「施設内虐待の被害者を救いたい」というメッセージ性をドラマに持たせ、被虐待者がフラッシュバックを来さない注意喚起がなされれば、社会はある程度それを許容するのではないかと思います。
このシーンは施設の子どもや職員の心を傷つけました。
しかし、放送の回数が重なるにつれて、施設長は「いい人」になっていきました。
第1回放送と別人格になってしまったかのような印象さえ受けます。
第1回放送における施設長の言動は、その後のドラマ展開に必要ないばかりか、一貫性のなさからすれば逆にドラマの質を下げる要因になったと思われます。
結果として、「あのようなシーンを出して何を伝えたかったのだろう?」という思いが残ります。
それでもあのシーンが必要だった理由を考えるとき、「センセーショナルなスタートを切って視聴者を引きつける」ところにあったのではないかと推測します。
作品からは子どもに対する愛情も感じられます。
それにも関わらず、問題として指摘される部分が生じました。
その原因は、現場の取材が少なかった事にあると考えます。
児童養護施設のお子さんと接し、職員の話を聞く時間を多く持っていただければ、今回のような事態には至らなかったと思います。
「この子たちのために、どのようなドラマにすべきか」という視点を持っていただけたはずです。例えば施設長の暴言シーンについても、制作会議で「そのシーンは、いくら何でもダメでしょう」という意見が出たと思います。
警察のドラマでは「警察官のために」という発想は必ずしも求められません。
銀行のドラマでも「銀行員のために」ではないようです。
実在の警察官や銀行員は苦々しい思いをされているかもしれませんが、それが人権侵害とまで言われるほどの社会の雰囲気ではありません。
しかし児童養護施設というテーマは、他と異なる対応を取っていただくべき分野です。
「視聴者に喜んでもらうために」「視聴者に感動してもらうために」という視点だけでなく、「この子どもたちのために」という観点から逸脱していないかを常にチェックしながら、制作していただきたい分野です。
「対象が子供」
「親と離れて生活せざるを得ない」
「6割が虐待を経験している」
児童養護施設とは、このような生活集団です。警察や銀行とは異なります。一般家庭から見れば異常とも受け取れる体験をし、心や体に傷を負った子どもがたくさんいます。
「結局、児童養護施設という舞台だけを利用されたという感じがします」
ある施設の子どもは、新聞の取材でこのようにコメントしていました。
子どもの心と体ではとても受け止められないような経験をした子どもたちを、ドラマで悲しませることがないように願います。
今回のドラマは9回シリーズでしたが、主に問題シーンが挿入されていたのは最初の2回でした。その後は次第に柔らかいトーンになり、感動的なシーンもありました。後半からドラマを見た人には、このドラマの問題点すら分からなくなるような内容です。
しかし、児童養護施設関係者からは、「1、2回目の放送で子どもを傷つけても、残りの放送分が感動的なら許されるのですか。傷つけられた者の癒やしにはなりません」という意見をいただきました。
前半でセンセーショナルな内容を提示し、残りの放送を和やかにハッピーエンドでまとめる手法は過去にも存在しました。手法そのものを否定する訳ではありませんが、「施設に入所した被虐待児」という社会的弱者を必然性の提示がないまま傷つけるとすれば問題です。
今後のドラマ制作に当たって、「最初は過激で問題にされる内容であっても、後が良ければ許される」風潮が残る事を危惧します。9回シリーズの中ではたった1回かもしれません。しかし1回でも、あるいはその中のほんの数分だとしても、公共放送の及ぼす影響は大きいのです。
いわゆる社会的弱者は要保護児童だけではありません。障がい者、被災者、貧困などテーマは多くあります。将来ドラマとして取り上げられる時に同じ問題が生じないことを願います。
「私のいた施設はドラマで描かれている施設よりもひどかった」
このようなご意見やご報告を複数いただきました。
施設でつらいご経験をなさった方のお気持ちをお察しいたします。
確かに昭和20~60年代においてはそのような施設が実在しました。
しかし施設では改善を繰り返し、以前とは異なる内容に変わりました。
子どもたちの安住のために努力している職員の皆さんを温かく見守っていただきたいと思います。
もちろん、現状の施設が完璧ではありません。
少ない予算、少ない人員で運営されているのが実情ですので、余裕がなく子どもにとっては必ずしも満たされた環境ではないかもしれません。
また、一部で虐待などのトラブルが発生しているのも事実です。
もしそのような事実があるとすれば、声をあげていただくべきだと思います。
施設出身の方も、施設職員の方も、私たちも、子どもの幸せを願う気持ちは同じです。お互い協力し、子どものためにより良い環境を目指せればと思います。
当院にも多くのご意見をいただき、参考にさせていただいたものも少なくありません。ただ残念なことは、多くの方が児童養護施設の実情と被虐待児の実情についてご存じないままお話になっていることです。
ドラマの第1、2回放送について問題点を指摘しているのは、当院だけではありません。全国児童養護施設協議会、全国里親会、日本こども虐待防止学会、浜松医科大学子どものこころの発達研究センターが要望書を提出しました。要養護児童や被虐待児と向き合っている人たちが危機感を持った表れです。
施設や被虐待児について何らかの経験や知識を持っている人はドラマの問題点を心配し、経験や知識をお持ちでない方は表現の自由が侵害される事を心配されているように思います。施設や虐待のことをご存じない方は、「クレーマーがテレビ局に圧力をかけた。乱暴だ。」と思われたかもしれません。
両者の意見がかみ合っていないもどかしさを覚えます。
「なぜ社会的養護の関係者がドラマを問題にしたのか?」
これを理解していただくために、児童養護施設や被虐待児の現実を知っていただきたいのです。施設の子どもに接していただき、職員の方の話をお聞きいただけませんか。全ての施設ではありませんが、ボランティア活動などを通じてそれが可能な所もあります。児童虐待については、インターネットでも体験談や事例を知ることができます。
児童養護施設、里親制度ともに喜びや幸せを感じながら過ごしている子は少なくありません。しかし、虐待の影響で病的な精神状態、肉体的後遺症に苦しんでいる子もいます。施設職員、里親はそれに向き合い改善の努力を行うのですが、力及ばず絶望的な状況に陥ることもあります。子どもには責任がないのに、その子が悲劇的な境遇から抜け出せない。そのような理不尽が存在します。
一人でも多くの方がこのような現実をお知りになり、ご理解・ご支援いただくことを願っています。